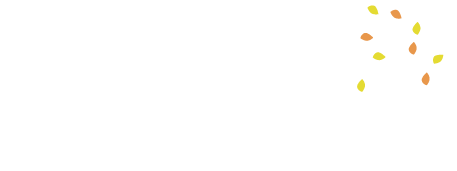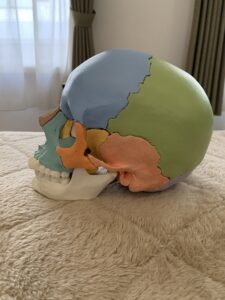陰と陽のバランスが、わたしの健康をつくる

施術をするときに、身体の状態を評価していくわけですが、その一つの視点として、陰陽論を使っています。
陰陽論(いんようろん)は、中国古代の自然哲学の基本的な考え方で、万物や現象を「陰」と「陽」という二つの対立的で、補い合う要素に分ける理論です。
陰と陽は絶対的な善悪や上下ではなく、相対的な関係
例:昼(陽)と夜(陰)、動(陽)と静(陰)、火(陽)と水(陰)。
どちらが正しい/優れているではなく、状況に応じて対になる。
陰陽の性質
陽:明るい、外向的、活動的、熱、上昇、男性性など
陰:暗い、内向的、静的、冷、下降、女性性など
陰陽の関係性(四大法則)
1. 対立:互いに反対の性質を持つ
2. 依存:どちらか一方だけでは存在できない(昼があるから夜がある)
3. 消長:一方が強くなれば、もう一方は弱まる(夏の陽が強まると陰が減る)
4. 転化:極まれば逆に変化する(夜が極まれば夜明け=陰から陽へ)
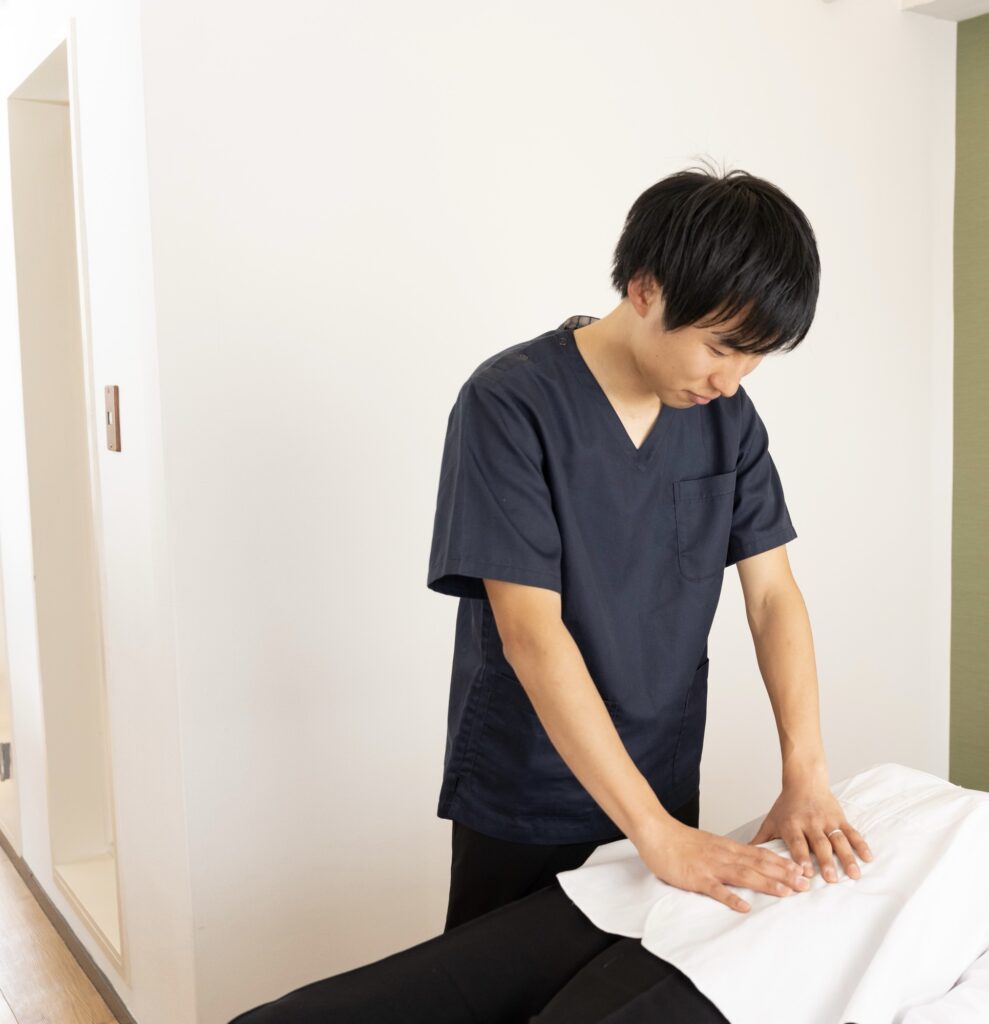
体質にも陰陽があります。
陰性体質・・・冷える、細い、軽い、顔が細長い、血圧低め、神経質、思考が活発、消化力弱い、疲れやすい
陽性体質・・・暑がり、筋肉質、重い、顔が丸い四角い、循環器に問題、陽気、肉体活動が得意、無理がきく
このような違いがあります。
ご自身やまわりの人を陰性か、陽性か想像してみるとおもしろいですよ。
そして、偏りすぎると、それぞれに問題が出てきます。
偏りすぎず、バランスを取っていくことを中庸といいます。
健康においても、中庸をとっていくことがとても大切になってきます。
休みすぎ(陰過剰)でも、働きすぎ(陽過剰)でもダメということです。

体質を改善していく上で、それぞれに合わせたアプローチが大事になってきます。
例えば、筋トレが健康にいいと言われても、陽性体質の人が過剰に行うと、問題が起きてきます。その場合は、同じ身体活動でも筋トレでなく、ウォーキングの方が良いことがあります。
逆に菜食がいいと言っても、陰性体質の方が葉物のサラダばかりを食べていると、エネルギー不足になり、不調が出てきます。野菜などでしたら、根菜類を摂ったり、お肉も食べ過ぎなければ、食べた方が体調は良くなります。

陰陽論という視点からも体質を考えると、クライアントさんの身体の状態を把握して、アプローチしていく上でとても役立っています。
整体サロンulurido(ユルリド)
田中裕貴